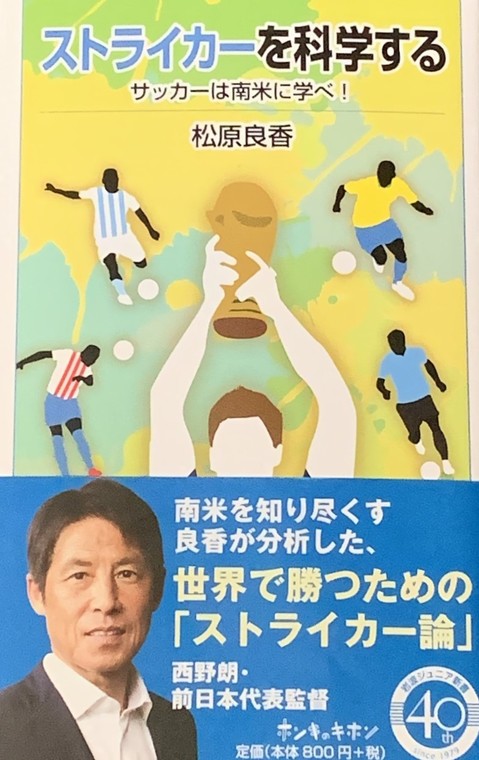南米・Jリーグ・欧州で戦ってきた松原良香の現在地 Vol.1
Jリーグではジュビロ磐田を皮切りに複数のチームで活躍し、ウルグアイ・クロアチア・スイスでもプレー経験のある松原良香さん。「国内外でどんなキャリアを歩んできたのか?そして現在はどのような活動をされているのか?」じっくり聞かせて頂いた。
――今年の高校サッカーは静岡学園(以下:静学)が優勝しましたね。松原さんは静岡出身ですし、今回の決勝戦も現場に行かれていましたが、いかがでしたか?
松原 静学が良かったのは、自分たちのスタイルで静岡らしくドリブルや足元で繋ぐ攻撃的なサッカーをしたこと。
あれは静岡県のスタイルだし、静学のユニフォームはカズさん(三浦知良)のいたブラジルのキンゼ・デ・ジャウーのユニフォームを真似て作ったものなんですよ。カズさんのお父さん、納谷宣雄さんが初代監督でした。
よくレガシーと言われますが、静学にはレガシーがあるんです。川口修監督に「静学で何を子供たちに教えているんですか?」と聞いたら「ハングリーさ」と言います。
勝ちたい欲とか、絶対に目の前の相手に負けないとか、湧き出てくる情熱、そこなんです。修さんもブラジルに行った経験があり、こんな話をしていました。
「1年半くらいブラジルに行きましたが、一緒にやっていた人が、次の日にいきなり解雇されてしまったんですよ。ただでさえ貧しいのにどうやって食べていくのか。そういう人達を目の当たりにしてきたんです。そんな厳しさを子供たちに伝えています」と言っていました。
もうひとつは井田勝通総監督の存在が大きいです。修さんが監督を引き継いで、同時に前監督の井田さんがベンチにいながら一緒にチームを作っているので、決勝戦のようなセットプレーからも得点するんです。今までの伝統と新しいセットプレーという両面を持ち合わせています。
足元の技術・個の技術とチームプレー、そしてセットプレーの強さの両面あります。静岡らしく勝ったのが何よりも嬉しく、次に繋がりますし、監督が代わるとサッカーが変わるチームが多いなかで、変わらずに、更に進化したのが素晴らしいですよね。
同じ静岡の清水エスパルスとジュビロ磐田にも頑張ってもらいたいです。
――松原さんはそのジュビロとエスパルスの他にもウルグアイ、クロアチア、スイスなど色々な国でプロサッカー選手としてプレーをされてきたので、特に海外の話を聞かせて頂きたいです。
松原 やはり海外の経験が大きいですね。
――高校を卒業してからウルグアイに行かれましたよね。当時は言葉も全くわからなかったり、カルチャーショックもあったと思います。南米の選手って自分のミスを「お前のせいだ!」と言ってくるじゃないですか。
松原 まさに言われました。でも、僕も言っていました(笑)。
――当時の松原さんは日本では高校生年代のエースストライカー。でもウルグアイでは誰も自分のことを知らないという状況ですよね。苦労など覚えていますか?
松原 僕がウルグアイへ渡った目的は、日本がアトランタオリンピックに出場するためでした。当時は日本が世界大会に出場することができなかった時代だったので、世界で戦うために、修行へ行ったというわけです。
よく覚えているのは、ウルグアイの空港に着いたら小さな空港で、まるでタイムマシーンで20年前に戻ってしまったみたいな感覚がしました。わかるでしょ?
――はい、同じ南米のボリビアでもそんな気がしました。
松原 着ているものが古かったり裸足の人がいたり。着いたら、日本人がいないじゃないですか。だからこそウルグアイへ行ったのですが、まず言葉が通じない。全てスペイン語なのが大変でした。
英語なんて南米の人はしゃべらないですよね。今でこそウルグアイ人も英語をしゃべるようになってきていますが。

――ボリビアでも英語は全く通じなかったです。
松原 空港に着いたら、少し寒い。僕は南米は一年中暑いのかと思っていましたが、そうじゃなかった。
――寒暖の差が激しい地域もありますよね。
松原 到着したら、子供たちがたくさん集まってきたんです。「俺って有名人?」と勘違いするぐらいで、要は、彼らはスーツケースや荷物を運んで、チップをもらいたいんです。よく見ると、貧しい子供たちでした。サッカー以前にそこからのスタートでしたね。
それがカルチャーショックというか、こんな感じなんだって思いました。親戚がアルゼンチンにいたことや、兄も約4年か5年くらいアルゼンチンに行っていたので、様子は聞いてはいたんですけどね。
あと静岡出身なので、ホンダや河合楽器やヤマハの工場が近くにあり、工場にブラジル人やコロンビア人、ペルー人などの南米の方がいたから、何となく雰囲気はわかったんですよ。着ているものや顔なども日本人とはちょっと違いますしね。

――ウルグアイに到着して驚いたことはありますか?
松原 最初にビックリしたことはタクシーに乗った時の話です。実はウルグアイが第1回ワールドカップ(1930年)の開催国なのですが、決勝戦などを行ったエスタディオ・センテナリオ(Estadio Centenario)を通ったときに、タクシー運転手が「エスタディオ、エスタディオ」って言ってきたんです。最初は何を言ってるかわかりませんでした。
――スペイン語でスタジアムという意味ですよね。
松原 そうです。後から勉強してスタジアムのことだと学びました。そして、泊まる場所に着くと、とても小さい狭い部屋でした。右隣と目の前がキャバレーでした。
あまり治安のよくない場所でした。「え?ここに住むの?」と思いました。ある程度覚悟はしていましたが。
スーツケースを持って、階段を上がって、扉を開けると狭くて狭くて。寝返りが出来ないくらいのベッドがひとつと、タンスがひとつ目の前にあって、あとはテーブルがあるだけ。テレビもありませんでした。
窓を開けると、隣のキャバレーからの大音量がすごかった。
「まじか、ここで1年間寝るのか、生活するのか」って思いましたね。不思議なことに、生活するうちにうるさい音には慣れていきましたが。
あの時は若かったので、異国の街や文化に興味があり、好奇心から街に繰り出しました。そんな中、多くの女性から声をかけられ、俺ってモテるな、なんて思っていました。何もわかっていませんでしたね。

――近隣の迷惑を考えずに、一晩中爆音を響かせている店などが南米にはありますよね。サッカー以前に生活がまず大変ですよね。
松原 まさにそうです。チームのトレーニングへ行った際は、ロッカールームでモノが無くなることが多々ありました。手袋が盗まれたり。トヨタカップに出場するような名門クラブでも、そんなことが起こる、そんな環境でした。
チームメイトに「メシ食いに行こう」と連れて行ったら、相手はお金を持っていなくて、僕がマックのハンバーガーをおごった記憶がありますが、そこから仲良くなったりしました(笑)。
あとは練習中の目の色が違いますよね。
――激しさが違いますよね。
松原 とんでもなく激しい。彼らは生きるためにサッカーをしています。僕が入ったチーム、ペニャロールは、ウルグアイでリーグ最多優勝回数を誇り、レアルマドリードで活躍するバルベルデなどのヨーロッパで活躍する選手を数多く輩出し、今はJリーグでもプレーしたフォルランが監督をしています。
当時は二軍でプレーしたので、早くトップチームに上がりたいという、若くていきがいい選手が沢山いました。トレーニングから気合がすごく、紅白戦は特にすごかったです。
僕の後ろをマークしながら、「日本人、バカヤロー」「ボール触ったら、お前削ってやる」とか叫んでるんですよ。それにも負けず僕もやり合いました。ユニフォームが破れることも多々ありました。
日本では手を使わないように教えられますが、ウルグアイでは真逆で、手を使って相手を押したり交わしたりしていました。
若いし、当時は「やられたら倍にして返す」と考えていたこともあり、「お前らには負けねぇ、同い年には負けねぇ」などいろいろ思いながら、毎日やっていました。
ロッカールームでチームメイトにからかわたときは、背負い投げをして日本の柔道を教えてあげました(笑)。

Vol.2へつづく
インタビューをさせて頂いた松原良香さんの本が発売中です。
【ストライカーを科学する~サッカーは南米に学べ】 https://www.iwanami.co.jp/smp/book/b473160.html
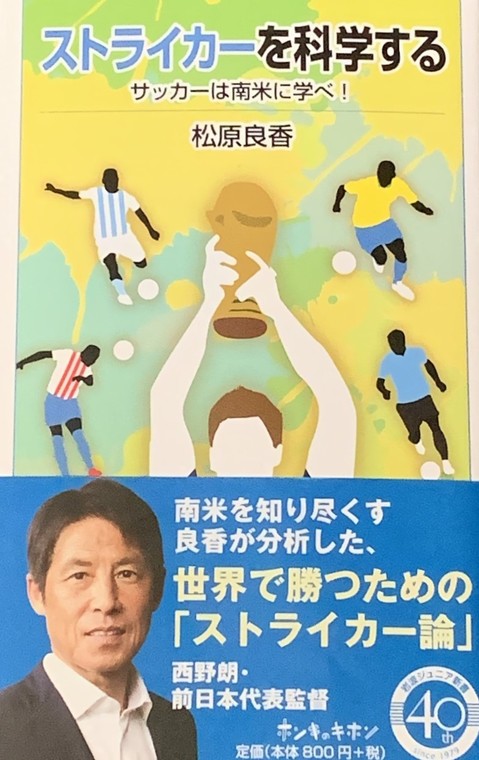
松原 静学が良かったのは、自分たちのスタイルで静岡らしくドリブルや足元で繋ぐ攻撃的なサッカーをしたこと。
あれは静岡県のスタイルだし、静学のユニフォームはカズさん(三浦知良)のいたブラジルのキンゼ・デ・ジャウーのユニフォームを真似て作ったものなんですよ。カズさんのお父さん、納谷宣雄さんが初代監督でした。
よくレガシーと言われますが、静学にはレガシーがあるんです。川口修監督に「静学で何を子供たちに教えているんですか?」と聞いたら「ハングリーさ」と言います。
勝ちたい欲とか、絶対に目の前の相手に負けないとか、湧き出てくる情熱、そこなんです。修さんもブラジルに行った経験があり、こんな話をしていました。
「1年半くらいブラジルに行きましたが、一緒にやっていた人が、次の日にいきなり解雇されてしまったんですよ。ただでさえ貧しいのにどうやって食べていくのか。そういう人達を目の当たりにしてきたんです。そんな厳しさを子供たちに伝えています」と言っていました。
もうひとつは井田勝通総監督の存在が大きいです。修さんが監督を引き継いで、同時に前監督の井田さんがベンチにいながら一緒にチームを作っているので、決勝戦のようなセットプレーからも得点するんです。今までの伝統と新しいセットプレーという両面を持ち合わせています。
足元の技術・個の技術とチームプレー、そしてセットプレーの強さの両面あります。静岡らしく勝ったのが何よりも嬉しく、次に繋がりますし、監督が代わるとサッカーが変わるチームが多いなかで、変わらずに、更に進化したのが素晴らしいですよね。
同じ静岡の清水エスパルスとジュビロ磐田にも頑張ってもらいたいです。
――松原さんはそのジュビロとエスパルスの他にもウルグアイ、クロアチア、スイスなど色々な国でプロサッカー選手としてプレーをされてきたので、特に海外の話を聞かせて頂きたいです。
松原 やはり海外の経験が大きいですね。
――高校を卒業してからウルグアイに行かれましたよね。当時は言葉も全くわからなかったり、カルチャーショックもあったと思います。南米の選手って自分のミスを「お前のせいだ!」と言ってくるじゃないですか。
松原 まさに言われました。でも、僕も言っていました(笑)。
――当時の松原さんは日本では高校生年代のエースストライカー。でもウルグアイでは誰も自分のことを知らないという状況ですよね。苦労など覚えていますか?
松原 僕がウルグアイへ渡った目的は、日本がアトランタオリンピックに出場するためでした。当時は日本が世界大会に出場することができなかった時代だったので、世界で戦うために、修行へ行ったというわけです。
よく覚えているのは、ウルグアイの空港に着いたら小さな空港で、まるでタイムマシーンで20年前に戻ってしまったみたいな感覚がしました。わかるでしょ?
――はい、同じ南米のボリビアでもそんな気がしました。
松原 着ているものが古かったり裸足の人がいたり。着いたら、日本人がいないじゃないですか。だからこそウルグアイへ行ったのですが、まず言葉が通じない。全てスペイン語なのが大変でした。
英語なんて南米の人はしゃべらないですよね。今でこそウルグアイ人も英語をしゃべるようになってきていますが。

――ボリビアでも英語は全く通じなかったです。
松原 空港に着いたら、少し寒い。僕は南米は一年中暑いのかと思っていましたが、そうじゃなかった。
――寒暖の差が激しい地域もありますよね。
松原 到着したら、子供たちがたくさん集まってきたんです。「俺って有名人?」と勘違いするぐらいで、要は、彼らはスーツケースや荷物を運んで、チップをもらいたいんです。よく見ると、貧しい子供たちでした。サッカー以前にそこからのスタートでしたね。
それがカルチャーショックというか、こんな感じなんだって思いました。親戚がアルゼンチンにいたことや、兄も約4年か5年くらいアルゼンチンに行っていたので、様子は聞いてはいたんですけどね。
あと静岡出身なので、ホンダや河合楽器やヤマハの工場が近くにあり、工場にブラジル人やコロンビア人、ペルー人などの南米の方がいたから、何となく雰囲気はわかったんですよ。着ているものや顔なども日本人とはちょっと違いますしね。

――ウルグアイに到着して驚いたことはありますか?
松原 最初にビックリしたことはタクシーに乗った時の話です。実はウルグアイが第1回ワールドカップ(1930年)の開催国なのですが、決勝戦などを行ったエスタディオ・センテナリオ(Estadio Centenario)を通ったときに、タクシー運転手が「エスタディオ、エスタディオ」って言ってきたんです。最初は何を言ってるかわかりませんでした。
――スペイン語でスタジアムという意味ですよね。
松原 そうです。後から勉強してスタジアムのことだと学びました。そして、泊まる場所に着くと、とても小さい狭い部屋でした。右隣と目の前がキャバレーでした。
あまり治安のよくない場所でした。「え?ここに住むの?」と思いました。ある程度覚悟はしていましたが。
スーツケースを持って、階段を上がって、扉を開けると狭くて狭くて。寝返りが出来ないくらいのベッドがひとつと、タンスがひとつ目の前にあって、あとはテーブルがあるだけ。テレビもありませんでした。
窓を開けると、隣のキャバレーからの大音量がすごかった。
「まじか、ここで1年間寝るのか、生活するのか」って思いましたね。不思議なことに、生活するうちにうるさい音には慣れていきましたが。
あの時は若かったので、異国の街や文化に興味があり、好奇心から街に繰り出しました。そんな中、多くの女性から声をかけられ、俺ってモテるな、なんて思っていました。何もわかっていませんでしたね。

――近隣の迷惑を考えずに、一晩中爆音を響かせている店などが南米にはありますよね。サッカー以前に生活がまず大変ですよね。
松原 まさにそうです。チームのトレーニングへ行った際は、ロッカールームでモノが無くなることが多々ありました。手袋が盗まれたり。トヨタカップに出場するような名門クラブでも、そんなことが起こる、そんな環境でした。
チームメイトに「メシ食いに行こう」と連れて行ったら、相手はお金を持っていなくて、僕がマックのハンバーガーをおごった記憶がありますが、そこから仲良くなったりしました(笑)。
あとは練習中の目の色が違いますよね。
――激しさが違いますよね。
松原 とんでもなく激しい。彼らは生きるためにサッカーをしています。僕が入ったチーム、ペニャロールは、ウルグアイでリーグ最多優勝回数を誇り、レアルマドリードで活躍するバルベルデなどのヨーロッパで活躍する選手を数多く輩出し、今はJリーグでもプレーしたフォルランが監督をしています。
当時は二軍でプレーしたので、早くトップチームに上がりたいという、若くていきがいい選手が沢山いました。トレーニングから気合がすごく、紅白戦は特にすごかったです。
僕の後ろをマークしながら、「日本人、バカヤロー」「ボール触ったら、お前削ってやる」とか叫んでるんですよ。それにも負けず僕もやり合いました。ユニフォームが破れることも多々ありました。
日本では手を使わないように教えられますが、ウルグアイでは真逆で、手を使って相手を押したり交わしたりしていました。
若いし、当時は「やられたら倍にして返す」と考えていたこともあり、「お前らには負けねぇ、同い年には負けねぇ」などいろいろ思いながら、毎日やっていました。
ロッカールームでチームメイトにからかわたときは、背負い投げをして日本の柔道を教えてあげました(笑)。

Vol.2へつづく
インタビューをさせて頂いた松原良香さんの本が発売中です。
【ストライカーを科学する~サッカーは南米に学べ】 https://www.iwanami.co.jp/smp/book/b473160.html