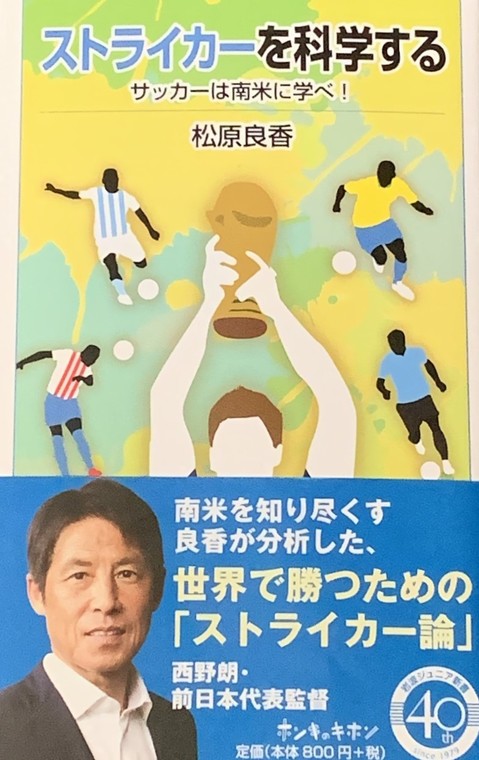南米・Jリーグ・欧州で戦ってきた松原良香の現在地 Vol.2
Jリーグではジュビロ磐田を皮切りに複数のチームで活躍し、ウルグアイ・クロアチア・スイスでもプレー経験のある松原良香さん。「国内外でどんなキャリアを歩んできたのか?そして現在はどのような活動をされているのか?」じっくり聞かせて頂いた。
Vol.1はこちらから
――ウルグアイの激しい毎日で、伸びていった感覚とかはありましたか?サッカーだけではなく、メンタル含めて。
松原 当時は無我夢中だったので、伸びているかどうかはわからなかったのですが、勝負に対する執着心が皆すごかったので、日本にいた頃より執着心を出すようになったと思います。そもそもこの頃の僕は感覚で生きていたように思います。
もともと遠慮せずに突進していくタイプだったので、ウルグアイは僕にピッタリ合いました。
日本では自分を前面に出していくことや勝負への執着心を抑えるような風潮だったのですが、ウルグアイでは反対で、自己主張することが普通で、サッカーをやっている時の彼らの真剣さは、普段とは真逆でした。
普段は冗談ばかり言っています。互いにからかい合ったり、自分の彼女や趣味の話をしたりするけれど、いざ練習になるとスイッチが入って、熱くなる。その切り替え具合は日本の選手と全く違いました。あれはすごかった。
僕には全てが新鮮で初めて体験するものだったので、自分が上手くなっているかどうかは、正直良くわかりませんでした。
ちなみに、ウルグアイでの生活でサッカー以外のスポーツに触れることや、話題にのぼることはありませんでした。それほどまでに、サッカーは国民の文化として根付いていました。
――サッカー自体は通用しましたか?質も違うので一概には言えないと思いますが。
松原 僕は点取り屋なので、ゴールを決めてなんぼじゃないですか。「でもボールが来ないし、触れもしない」、そんな状況でした。それが一番困ったことです。何で自分にこんなにボールが来ないのか、と思いました。
やっぱりその状況を理解し適応していくことが大事です。最初は、ボール回しをウォーミングアップでやったりして、段々と信頼関係を築いていくのです。
「この日本人やるな」とか、認められるようになることが大変でした。彼らは、上手いか下手かをみています。ピッチの中で見せるのが効果的ですが、オフザピッチのところでもコミュニケーションをとっていました。
行き帰りのバスや、歩いている時、パーティーなどプライベートの時間、さらに打ち解けてくると食事を家に招待される時とかに。あとは一緒にディスコに行くとか(笑)
そういうところですね。もともと好奇心旺盛で、人と接するのが好きだったので、自分から積極的にコミュニケーションを取りに行っていました。誘われたら、ほとんど断らず、ノリよく行っていました。

――言葉も覚えていきましたか?
松原 言葉を覚えるのもやっぱり自分が悔しい思いをした時や、やりたいことができない時とかですね。「パスくれよ」って言えないとくれないから。1回や2回だけではなく、何回もボールに触りたい。スペイン語を覚えて「Dame la pelota!」(ボールくれよ!)と。
「なんで俺は試合に出られないの?」と監督に直接聞きにいったりしました。南米は選手から監督に対して積極的にコミュニケーションを取るのが基本ですから。待つのではなく、自分からスペイン語で話しかけていくことが大切でした。
黙っていれば感じてくれる「察する」という感覚は南米の人にはないので、こっちがしっかり言ったり伝えないと相手はわからないです。
――コミュニケーションのところですね。
松原 あとはプライベートです。その国の文化を知らないといけません。異国の文化を知るようになるとは、ウルグアイに行くまでの僕は微塵も思っていませんでしたが、彼らが言うアッサードを食べたり、マテ茶を飲んだり、甘いものを食べたり真似ていました。
――ウルグアイには約一年いたと思いますが、だんだんと認められてボールも集まってくるようになったのですか?
松原 そうですね。僕の実力も見てくれていたと思いますが「トップで使ってやれ」とか「こいつはオリンピックの候補にも入っているから」など、クラブ間(ペニャロールとジュビロ)でそういう話もあったのではないのかと予想しています。
それでトップの練習の紅白戦に途中から出してくれたり、時々頭から出してくれる時もありました。でも、そこは自分の得意なポジションじゃなくて、左ウィングだったりしました。
4・4・2の左とか、右とか。空いているポジションで使ってくれる感じです。そんな扱われ方なんかも自分なりに多少感じていました。
でも、ウルグアイのペニャロールと言えば、20世紀に最も成功した南米のクラブと言われるほどで、そのトップチームでプレーできること自体、W杯に出場したことのなかった日本人からすると、信じられないことでした。


――かなりの名門ですよね。
松原 名門もなにも南米のビッグクラブ。その後ヨーロッパで活躍する良い選手を数多く輩出しているし、南米・世界でも知らない人はいない。
そこでウルグアイ代表選手や、これから世界で活躍するであろうダイヤモンドの原石たちと一緒にやらせてもらうというのは、高校あがりの自分にとってはすごくドキドキしたのは覚えています。
――プレーは、けっこうできた感じでしたか?
松原 できたというか、迷惑をかけないように、自分なりに一生懸命やりましたが、自分の特徴・役割であるゴールに向かっていくことはあまりできませんでした。
そのような場面でもチャンスをものにし点を取れるような若手の選手が、その後世界へ出ていくことができるのだと思います。
基本、どこのエリアでも真ん中あたりでは、ウルグアイのサッカーではハードにくるんです。ゴールに近くなればなるほどプレスが激しい。やらせるところと、やらせないところの差が凄くはっきりしていました。
だから、中央のところに入っていこうとした時は、スライディングで足ごとボールを狩りにこられるので、もの凄くプレッシャーを感じました。
スポーツというより、サッカーという名の生き残りをかけた戦いです。よりサイドの方だと、ボールを持たせてくれ、そこまでプレッシャーは来ません。1軍と2軍では質が全く違ったし、あの空気感が何とも言えませんでした。
最初、チームに認めてもらいたいとか、ミスしないようにということばかり思っていました。もう一歩先に踏み込んで、一番危険なところで勝負したりすれば良かったと今は思います。当時はなんせ高校あがりだったので。
イケイケの自己中心的だった自分が、周りの環境もあり、状況に合わせないといけない、ペニャロールの一員になりたい、ということを意識しプレーしていました。
いきなり上手い代表選手たちと一緒にやることに、ちょっと気が引けたところは正直ありました。 そのような経験も含めて、ウルグアイではサッカーは戦いであり、原理原則であるゴールを奪うこと、ゴールを守ること、自分の仕事に集中しチームに貢献すること、その為にスペイン語を覚えること、またどんなに良いプレーをしても結果が全てで結果で評価されるんだということを学びました。
――その時に、松原さんは何のスパイクを履いていたか覚えていますか?
松原 当時は東海大一高校がアシックスを使っていました。そのままアシックスを履いていたと思います。途中からはジュビロがプーマだったので、プーマを提供してもらって履いていたと思います。南米ではみんなスパイクを欲しがりますよね。
――くれくれとか、履かせろとか。
松原 そうそう。お金がなくて彼らに日本から持ってきたスパイクを売りました(笑)でも自分のスパイクがないとサッカーできないので、自分のスパイクは死守していました。
――チームメイトはどこのスパイクを履いていたんですかね?
松原 トッパーとかだったかな。プーマ、アディダスを履いていた選手はいましたが、当時はナイキを履いている選手はいなかったと思います。あとは日本では見ないメーカーもありました。
――日本のスパイクを履いたら上手くなると思い込んでいる選手がいて、「一回履かせろ」って言って返してくれないことがボリビアでありました(笑)
松原 まさに(笑)彼らはもらえたらラッキーと思っていて、そういったところは隙を逃さない。あわよくばもらおうと狙っていると言った方が適切かもしれません。それが良くも悪くも南米の流儀なのだと思います。
Vol.3へつづく
インタビューをさせて頂いた松原良香さんの本が発売中です。
【ストライカーを科学する~サッカーは南米に学べ】 https://www.iwanami.co.jp/smp/book/b473160.html
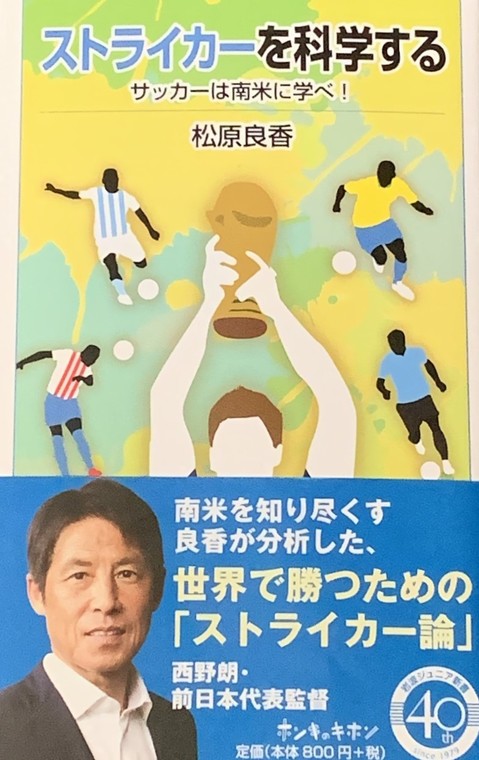
――ウルグアイの激しい毎日で、伸びていった感覚とかはありましたか?サッカーだけではなく、メンタル含めて。
松原 当時は無我夢中だったので、伸びているかどうかはわからなかったのですが、勝負に対する執着心が皆すごかったので、日本にいた頃より執着心を出すようになったと思います。そもそもこの頃の僕は感覚で生きていたように思います。
もともと遠慮せずに突進していくタイプだったので、ウルグアイは僕にピッタリ合いました。
日本では自分を前面に出していくことや勝負への執着心を抑えるような風潮だったのですが、ウルグアイでは反対で、自己主張することが普通で、サッカーをやっている時の彼らの真剣さは、普段とは真逆でした。
普段は冗談ばかり言っています。互いにからかい合ったり、自分の彼女や趣味の話をしたりするけれど、いざ練習になるとスイッチが入って、熱くなる。その切り替え具合は日本の選手と全く違いました。あれはすごかった。
僕には全てが新鮮で初めて体験するものだったので、自分が上手くなっているかどうかは、正直良くわかりませんでした。
ちなみに、ウルグアイでの生活でサッカー以外のスポーツに触れることや、話題にのぼることはありませんでした。それほどまでに、サッカーは国民の文化として根付いていました。
――サッカー自体は通用しましたか?質も違うので一概には言えないと思いますが。
松原 僕は点取り屋なので、ゴールを決めてなんぼじゃないですか。「でもボールが来ないし、触れもしない」、そんな状況でした。それが一番困ったことです。何で自分にこんなにボールが来ないのか、と思いました。
やっぱりその状況を理解し適応していくことが大事です。最初は、ボール回しをウォーミングアップでやったりして、段々と信頼関係を築いていくのです。
「この日本人やるな」とか、認められるようになることが大変でした。彼らは、上手いか下手かをみています。ピッチの中で見せるのが効果的ですが、オフザピッチのところでもコミュニケーションをとっていました。
行き帰りのバスや、歩いている時、パーティーなどプライベートの時間、さらに打ち解けてくると食事を家に招待される時とかに。あとは一緒にディスコに行くとか(笑)
そういうところですね。もともと好奇心旺盛で、人と接するのが好きだったので、自分から積極的にコミュニケーションを取りに行っていました。誘われたら、ほとんど断らず、ノリよく行っていました。

――言葉も覚えていきましたか?
松原 言葉を覚えるのもやっぱり自分が悔しい思いをした時や、やりたいことができない時とかですね。「パスくれよ」って言えないとくれないから。1回や2回だけではなく、何回もボールに触りたい。スペイン語を覚えて「Dame la pelota!」(ボールくれよ!)と。
「なんで俺は試合に出られないの?」と監督に直接聞きにいったりしました。南米は選手から監督に対して積極的にコミュニケーションを取るのが基本ですから。待つのではなく、自分からスペイン語で話しかけていくことが大切でした。
黙っていれば感じてくれる「察する」という感覚は南米の人にはないので、こっちがしっかり言ったり伝えないと相手はわからないです。
――コミュニケーションのところですね。
松原 あとはプライベートです。その国の文化を知らないといけません。異国の文化を知るようになるとは、ウルグアイに行くまでの僕は微塵も思っていませんでしたが、彼らが言うアッサードを食べたり、マテ茶を飲んだり、甘いものを食べたり真似ていました。
――ウルグアイには約一年いたと思いますが、だんだんと認められてボールも集まってくるようになったのですか?
松原 そうですね。僕の実力も見てくれていたと思いますが「トップで使ってやれ」とか「こいつはオリンピックの候補にも入っているから」など、クラブ間(ペニャロールとジュビロ)でそういう話もあったのではないのかと予想しています。
それでトップの練習の紅白戦に途中から出してくれたり、時々頭から出してくれる時もありました。でも、そこは自分の得意なポジションじゃなくて、左ウィングだったりしました。
4・4・2の左とか、右とか。空いているポジションで使ってくれる感じです。そんな扱われ方なんかも自分なりに多少感じていました。
でも、ウルグアイのペニャロールと言えば、20世紀に最も成功した南米のクラブと言われるほどで、そのトップチームでプレーできること自体、W杯に出場したことのなかった日本人からすると、信じられないことでした。


――かなりの名門ですよね。
松原 名門もなにも南米のビッグクラブ。その後ヨーロッパで活躍する良い選手を数多く輩出しているし、南米・世界でも知らない人はいない。
そこでウルグアイ代表選手や、これから世界で活躍するであろうダイヤモンドの原石たちと一緒にやらせてもらうというのは、高校あがりの自分にとってはすごくドキドキしたのは覚えています。
――プレーは、けっこうできた感じでしたか?
松原 できたというか、迷惑をかけないように、自分なりに一生懸命やりましたが、自分の特徴・役割であるゴールに向かっていくことはあまりできませんでした。
そのような場面でもチャンスをものにし点を取れるような若手の選手が、その後世界へ出ていくことができるのだと思います。
基本、どこのエリアでも真ん中あたりでは、ウルグアイのサッカーではハードにくるんです。ゴールに近くなればなるほどプレスが激しい。やらせるところと、やらせないところの差が凄くはっきりしていました。
だから、中央のところに入っていこうとした時は、スライディングで足ごとボールを狩りにこられるので、もの凄くプレッシャーを感じました。
スポーツというより、サッカーという名の生き残りをかけた戦いです。よりサイドの方だと、ボールを持たせてくれ、そこまでプレッシャーは来ません。1軍と2軍では質が全く違ったし、あの空気感が何とも言えませんでした。
最初、チームに認めてもらいたいとか、ミスしないようにということばかり思っていました。もう一歩先に踏み込んで、一番危険なところで勝負したりすれば良かったと今は思います。当時はなんせ高校あがりだったので。
イケイケの自己中心的だった自分が、周りの環境もあり、状況に合わせないといけない、ペニャロールの一員になりたい、ということを意識しプレーしていました。
いきなり上手い代表選手たちと一緒にやることに、ちょっと気が引けたところは正直ありました。 そのような経験も含めて、ウルグアイではサッカーは戦いであり、原理原則であるゴールを奪うこと、ゴールを守ること、自分の仕事に集中しチームに貢献すること、その為にスペイン語を覚えること、またどんなに良いプレーをしても結果が全てで結果で評価されるんだということを学びました。
――その時に、松原さんは何のスパイクを履いていたか覚えていますか?
松原 当時は東海大一高校がアシックスを使っていました。そのままアシックスを履いていたと思います。途中からはジュビロがプーマだったので、プーマを提供してもらって履いていたと思います。南米ではみんなスパイクを欲しがりますよね。
――くれくれとか、履かせろとか。
松原 そうそう。お金がなくて彼らに日本から持ってきたスパイクを売りました(笑)でも自分のスパイクがないとサッカーできないので、自分のスパイクは死守していました。
――チームメイトはどこのスパイクを履いていたんですかね?
松原 トッパーとかだったかな。プーマ、アディダスを履いていた選手はいましたが、当時はナイキを履いている選手はいなかったと思います。あとは日本では見ないメーカーもありました。
――日本のスパイクを履いたら上手くなると思い込んでいる選手がいて、「一回履かせろ」って言って返してくれないことがボリビアでありました(笑)
松原 まさに(笑)彼らはもらえたらラッキーと思っていて、そういったところは隙を逃さない。あわよくばもらおうと狙っていると言った方が適切かもしれません。それが良くも悪くも南米の流儀なのだと思います。
Vol.3へつづく
インタビューをさせて頂いた松原良香さんの本が発売中です。
【ストライカーを科学する~サッカーは南米に学べ】 https://www.iwanami.co.jp/smp/book/b473160.html